第10回 小さなお茶会ご報告
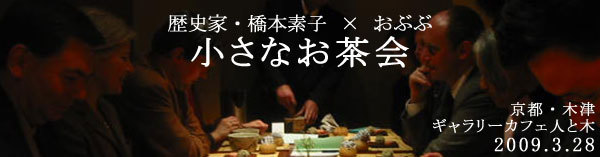
この日は、京都・木津の古民家を改修したギャラリーカフェ「人と木」で、歴史家・橋本素子さんをお招きし、「小さなお茶会」を開催いたしました。
(通称:もちやさん)
今回のゲスト、橋本素子さん(通称もちやさん)は、中世における宇治茶(お茶)研究の第一人者。
そして今回のテーマは、
「宇治茶とは何か?」
この日は、
宇治茶について、歴史的な観点から、もちやさんにお話いただきました。
大画面でみる
そもそも今回のお茶会のきっかけは、こちらのテレビ放送でした。
現在の宇治茶の定義は、
「京都・奈良・滋賀・三重の四府県産茶で、京都府業者が府内で仕上げ加工したもの」
と、されています。(宇治茶の定義より)
これは、2004年、(社)京都府茶業会議所によって、定められた自主基準です。
>>「宇治茶の定義」について
この映像は、現在の「宇治茶の定義」から見た場合、一見正しいように感じます。
しかしながら、
700年つづく宇治茶の歴史から見ると、宇治茶の産地である「宇治」は生産地としてだけでなく、全国からの茶の集散地としても発展してきました。
歴史的にも400年以上むかしには、すでに「宇治」に茶が集まっていたという史実もあります。
もっとも当時の「宇治」は、現在の宇治市よりももっと小さな範囲で「宇治郷」と呼ばれる地域の茶師が取りあつかう茶葉が、宇治茶だったようです。
天正12年(1584年)に著された、『羽柴秀吉禁制』にも禁制事項の一つに
「他郷の者、宇治茶と号し、銘袋を似せ、諸国に至りて商売せしむ事
(他地域の者が、宇治茶と称し、包装を似せて、全国で商売すること)」という内容がが記載されているとのこと。
つまり、400年以上のむかし、すでに宇治茶のブランドは、その名を全国に知られており、ニセモノを取り締まる必要があるくらいだったようです。(笑)
そして当時より、「宇治」が産地としてだけでなく、茶の集散地として機能していたこともこの一文よりうかがえます。
また注目すべきふたつ目のポイントは、
禁制している内容が、「他郷の者、宇治茶と号し~、」となっており、
「宇治以外で採れたお茶は、宇治茶と称してはいけない」のではなく、
「宇治以外の者が、宇治茶と称してはならない」となっている点。
つまり、「宇治以外でとれたお茶も宇治の茶師が宇治茶であると称すればよい。」わけで、
当時から宇治には、さまざまな産地よりお茶が集まっていたことはまちがいないようです。
まとめるなら、
宇治茶の歴史は、800年以上におよび、そのブランドは400年以上の昔から全国に知れ渡っていた。
それを今から100年ほど前にできた行政区分である、京都府や宇治市などのくくりで定義するのは、
そもそもかなりむつかしいことなのでしょう。
という感じで、今回は僕たちもかなり勉強させていただいたお茶会でした。
そして、
硬めの内容のあとには、おぶぶのお茶と和菓子をお楽しみいただきました!
おぶぶの取組みやお茶について、お茶と和菓子をお楽しみいただきながら、ざっくばらんにお話させていただきました。
今回、すばらしい場所をご提供くださった、人と木のオーナー森田さん、
それから、宇治茶の歴史について、お話くださったもちやさん、
そして、お集まりくださった皆さま、
ほんとうにありがとうございました!!
次回は、いよいよ5月の茶摘体験!
楽しい企画にできるように準備いたしますので、乞うご期待です!^v^
>>次回、茶摘体験の案内をみる
参加者様からいただいたご感想
![]()
-

- 大阪府堺市Sさま(女性)
![]()
-

- 京都府山城町Wさま(女性)

- 奈良県大和郡山市Mさま(男性)
- 【ブログでのご紹介】ティージョルノさま
【ブログでのご紹介】本日の講師・もちやさん


この記事を書いたおぶぶメンバー-Author Profile

このおぶぶメンバーの他の記事-Latest entries
 おぶぶについて2022 年 8 月 15 日茶畑でカマキリ発見!~春夏編~
おぶぶについて2022 年 8 月 15 日茶畑でカマキリ発見!~春夏編~ おぶぶについて2022 年 8 月 8 日おぶぶ茶苑のボランティアに参加しました!
おぶぶについて2022 年 8 月 8 日おぶぶ茶苑のボランティアに参加しました! 平安女学院さんとコラボ作品集2021 年 7 月 30 日おぶぶWalker by 平安女学院大学の女子大生ボランティア
平安女学院さんとコラボ作品集2021 年 7 月 30 日おぶぶWalker by 平安女学院大学の女子大生ボランティア おぶぶについて2020 年 11 月 11 日【活動報告】おぶぶスタッフもえちゃんの共同研究が本の一章として採択され出版されました!
おぶぶについて2020 年 11 月 11 日【活動報告】おぶぶスタッフもえちゃんの共同研究が本の一章として採択され出版されました!

